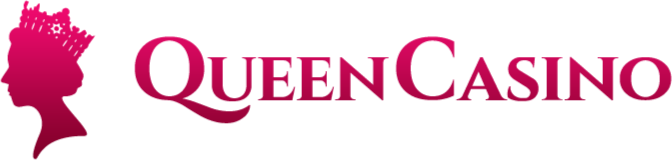当サイトからご登録いただいたユーザー様限定の特別ボーナスをご用意しています!
まず初めに登録するだけで、入金不要で88ドルと88回のフリースピンをお楽しみいただけます。
入金不要ボーナスを使用後に入金していただいた場合には、特別入金不要ボーナスをプレゼントいたします。
通常1回しかもらえない初回入金ボーナスが2回もらえちゃいます!
1回目の初回入金ボーナス:100%入金ボーナス→3倍の賭け条件を満たせば出金が可能です。
2回目の初回入金ボーナス:100%入金ボーナス→25倍の賭け条件を満たせば出金が可能です。